生きる力で地域を育てる〜福祉教育・福祉体験プログラム
高校生福祉体験学習〜はまゆうキャンプ〜
|
|
 なぜ体験学習か なぜ体験学習か高校生が福祉について学ぶ方法、いわば福祉教育にはいろいろな方法がある。福祉そのものについてもいろいろな考え方がある。 横須賀市社会福祉協議会(以下、市社協)では、「高校生」という最も多感な時に、地域に密着した福祉について、 それはとりも直さず人権の問題でもあるが、取り組んでほしいと考えた。 地域にはさまざまな人がいる。いろいろな条件のもとで一生懸命生きている。まずそれを直視してほしい。 そして一人ひとりがみな違っている。この「みな違っている」ということが当然と受け止めることができるようになってほしい。 福祉の基本としてぜひこのことは学ぶ必要があると考えた。頭ではなく、心で理解してほしい。話して聞かせることは簡単だ。 理屈ではない。だから、ふれあって、体験して学ぶ。これが学習方法として最適ではないか。 人間として生きていくうえで絶対に必要なことであるから、実際にふれて、体験して学ぶ、 体験学習が必要なのである。高校生一人ひとりが、それぞれ体験し、ふれあって、感じて、 何かを考える、それが『はまゆうキャンプ』である。 市社協では、『はまゆうキャンプ』の目的を地域にさまざまな立場の人がいることを学び、そのようななかで、 自分たちが果たせる役割は何かを学ぶこと、としているが、体験というインパクトの強い学習方法で多くの 感動を味わいながら着実に成果を上げている。 |

|
 25年間の歴史 25年間の歴史『はまゆうキャンプ』は、ある高校の先生から、「生徒にボランティアの体験をさせたいが、 市社協として取り組んでいただけないか」という話から始まった。昭和51年のことである。 市社協もたまたま高校生を対象とした福祉教育事業を考えていたので、実施を前提に、「どのような形で実施するか」 ということで企画会議をもった。なにしろ何もないところから計画を立てるわけだから議論百出であった。 「高校生には無理」だとか、「事故があったらどうするのか」とか、「どこか他でやっているのか」という意見もあった。 その一方で、「福祉といっても基本的なことなので体験学習がよいのではないか」「福祉とは人間を学ぶこと、 1週間ぐらい泊まり込んでやるべき」などの意見も出た。 そうした話し合いを経て、第1回目を次の通り実施した。この3泊4日の宿泊型福祉体験学習は、平成8年まで続いた。
|
|
参加者説明会
昭和53年度、このキャンプの名称を『はまゆうキャンプ』とした。これは、夏に白い花を咲かせる『はまゆう』が、
当時の市民投票で市の花に決まったので、夏、清らかな白い花、高校生という連想で決めたものである。
このキャンプを記録するため、映画『老人と高校生』を撮った。 年々、キャンプに参加する高校生が増加し、利用できる施設も増えてきた。毎年キャンプ終了後、施設、学校、市社協で 反省会を開催し、翌年にそれを生かしていくという方法で実施してきた。
平成9年度からは、学校側から強い要望があった保育園でのキャンプについて実施することにし、それに伴ってキャンプの方法を
変えた。これまで3泊4日の宿泊で実施していたキャンプを3日間の通所ということにした。
開始当初は、お寺などを借用して宿泊していたが、この頃になると施設側も整備され、その施設に宿泊する
ということが多くなってきていた。 |
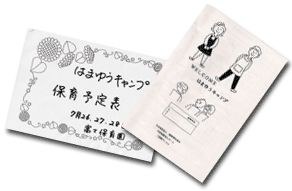 昭和54年度、2つの老人施設に加えて、この年から障害者施設1施設が利用できることになった。
昭和54年度、2つの老人施設に加えて、この年から障害者施設1施設が利用できることになった。